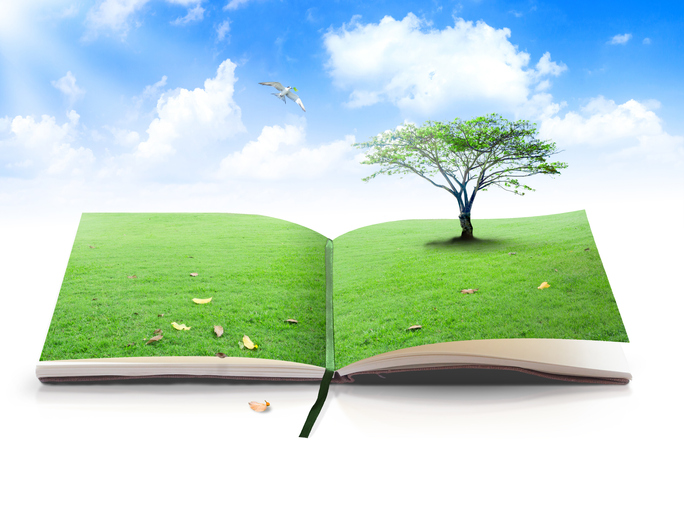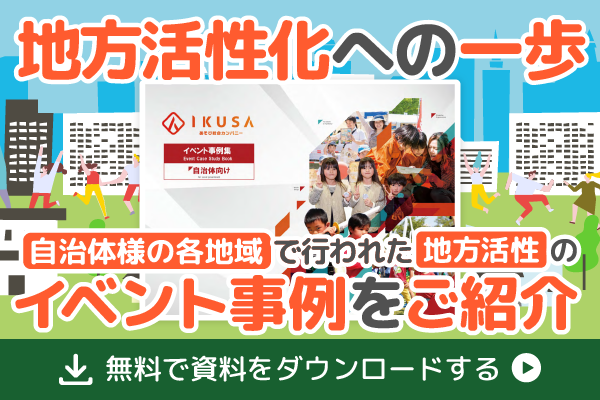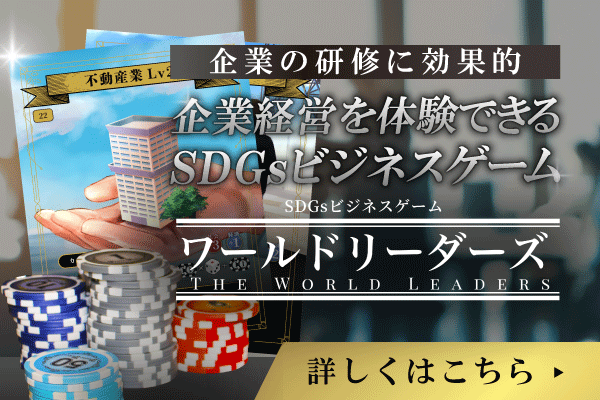SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」の概要と取り組みをわかりやすく解説

「SDGsについて興味があるけど具体的に何をすればいいの?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
SDGsには17の目標があり、まずはそれぞれの目標について理解を深め、「自社の事業と関連が深そうな目標は何か?」を見定めることが大切です。
全部で17あるSDGsの目標のうち「4・質の高い教育をみんなに」は、主に「教育」へ目を向けた目標です。
SDGsのはじめの一歩を実現する「SDGsの社内浸透方法」とは?
\SDGsイベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
目次
SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」とは

SDGsの目標17のうち、4として設定されている「質の高い教育をみんなに」は、子どもの教育機会を確保するだけではなく、仕事に就くために「大人」の教育も視野に入れた目標です。
日本では小学校から中学校まで義務教育として定められていて、すべての子どもが教育を受けられるようにしてあります。また、金銭的な理由などから大学へ進学できない人に対しては奨学金という形で教育資金を貸し出すなど、教育機会を逃さないための工夫が施されています。
しかし、世界に目を向けてみると、日本のように「ほとんどの子どもが学校に通える」という国ばかりではありません。「学校に通えるのは一部の富裕層のみ」「差別により学校へ通うことが認められていない」など、さまざまな背景により、教育機会を得られない人々がいます。
SDGs目標4は、こうした背景から、すべての人々が教育を受けられるようにするために策定されたのです。
すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
「教育」と聞くと、子どもが対象なのでは? といったイメージがありますが、大人も例外ではありません。生涯学習の機会を促進することも目標なので、仕事を得るための教育や研修を受けられるようにすることなどもSDGsの目標に該当します。
また、この目標のポイントは、単純に教育制度を充実させることだけではなく「包摂的かつ公平で質の高い教育を提供すること」です。つまり、社会的に弱者と言われる立場の人々も、質の高い教育を受けられるようにすることが大きな目標と言えます。
数字で見る「教育」の現状
現在、開発途上国の初等教育(小学校など)就学率は90%を超えているものの、学校に通えていない子どもはおよそ5,700万人にも及びます。学校に通えていない子どもの半分以上が、貧困問題が深刻であるサハラ以南アフリカで暮らしています。
ちなみに、初等教育を受けられていない子どものおよそ3分の1は、紛争地や被災地に住んでいると考えられています。そして、全世界で6億1,700万人の若者が、算術や読み書きができないという事実があります。
SDGsの社内浸透にお困りですか? SDGsコンパスなら体験を通してSDGsを楽しく学べます!
⇒SDGsコンパスの資料を見てみたい
SDGsの目標4における7つの達成目標

SDGsの目標4には、大きく7つの達成目標があります。具体的な内容は、子どもの教育と、若者の能力の向上、仕事に関する大人の能力向上です。
質の高い教育を誰もが受けられるようにすることは、決して簡単なことではありません。しかし、より良い社会・国をつくるうえで教育は必要不可欠なのです。達成目標の詳細や、どのように達成するのかなどについて、詳しく紹介していきます。
1.すべての子どもが小学校と中学校を卒業できるようにする
- “2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。”
SDGsの目標4における達成目標の一つが、「すべての子どもが小学校と中学校を卒業できるようにする」ことです。
日本では、小学校と中学校を卒業することはもはや当たり前となっています。しかし、本記事ですでに触れている通り、世界に目を向けてみると、そもそも小学校にも就学できないという子どもは少なくありません。
学校に行くお金がなかったり、家族を養うために働かなければならなかったりなど、理由はさまざまです。SDGsの目標4では、「すべての子ども」が小学校及び中学校を卒業することを目標としています。開発途上国を中心に、子どもが教育を受けられる社会環境を整えなければなりません。
2.すべての子どもが小学校にあがるための準備ができるようにする
- “2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、質の高い早期幼児の開発、ケア、および就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うようにする。”
子どもの教育は小学校から、というイメージがあります。しかし、教育は必ずしも小学生からとは限りません。保育園や幼稚園などでも人との関わりを学んだり、社会のルールに触れたりします。また、施設によっては小学校で学ぶ教育に少し触れるなど、小学校に通う前にある程度学習の習慣を身につけることもあります。
いずれにせよ、すべての子どもが小学校にあがる前に、幼稚園や保育園などで「小学校にあがるための準備」をする機会を得ることは重要なことです。
3. 大学を含めた高等教育を受けられるようにする
- “2030年までに、すべての人々が男女の区別なく、安価で質の高い技術教育、職業教育、および大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。”
開発途上国における高等教育に通う人の割合は、先進国と比べて著しく低い状況です。これは、金銭的な問題のみならず、性別による差別なども挙げられます。女性は教育の優先度が低く見られる場合があり、男性と比べて高等教育の就学が低い傾向にあるのです。
しかし、貧困を解消したり、すべての人が豊かに暮らしたりためには、性別に囚われることなく教育を受けられるような環境を確立しなければなりません。
4.仕事に関する技術や能力を持つ大人を増やす
- “2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、ディーセント・ワークおよび起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。”
開発途上国では、仕事の賃金と労力が見合っていなかったり、人間らしさに欠ける仕事であったりといったケースが少なくありません。仕事の能力を持っている大人を増やさなければ、国が豊かになりませんし、貧困の解消も難しくなってしまいます。
国全体が現在の環境を変えるためにも、仕事に関する技術及び能力を持つ大人を増やし、社会に貢献できるように目指していかなければならないのです。
5.教育における性別や障がいなどの差別を解消する
- “2030年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民および脆弱な立場にある子どもなど、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等にアクセスできるようにする。”
いまだ教育における性別や障がいの差別はなくならないのが現状です。実際「女の子は教育の必要がない」と考える地域があったり、宗教の関係上で男の子のほうが教育において優遇されるケースが見られたりします。
SDGs目標4では、こうした性別や、障がいの有無などで教育を受ける機会が不平等にならないよう目指します。
6.すべての若者や大人が読み書きや計算ができるようにする
- “2030年までに、すべての若者および成人の大多数(男女ともに)が、読み書き能力および基本的計算能力を身に付けられるようにする。”
主に開発途上国のなかには十分に教育を受けられず、算術や読み書きができない多数の若者や大人がいます。
SDGs4の目標では、こうした若者・大人をなくし、すべての人が文字の読み書きも計算もできるようにすることを目標としています。
7. 持続可能な社会をつくるために必要な知識・技術を身につけられるようにする
- “2030年までに、持続可能な開発と持続可能なライフスタイル、人権、ジェンダー平等、平和と非暴力の文化、グローバル市民、および文化的多様性と文化が持続可能な開発にもたらす貢献の理解などの教育を通じて、すべての学習者が持続可能な開発を推進するための知識とスキルを獲得するようにする。”
SDGsを達成し、持続可能な社会をつくるためには、それに必要な知識や技術を全ての人が身につける必要があります。例えば、人権や平和、文化などを学ぶための教育を進める必要があります。
達成するための具体的な方法3つ

SDGsの目標4を達成するにあたり、具体的な方法として挙げられるのは以下の3つです。
1.奨学金制度の推進
達成するための方法として、まず挙げられるのが奨学金制度の推進です。貧困世帯など、高等教育に就学することが難しい人の場合、修学のお金を確保するのは難しい現状があります。その場合は、奨学金制度を活用して希望する教育を受けられるように促したり、利用できる奨学金制度の数を増やしたりする必要があるでしょう。
日本でも金銭事情を理由に大学進学を諦めるケースがありますが、奨学金制度の選択肢があることを理解することで、進路の幅も広がる可能性もあります。国を問わず、奨学金の制度をつくり、認知を進めていくことが大切です。
2.質の高い教員の確保
教育において不可欠である教員。しかし、その質は個人差が大きいのが現状です。子どもなど、教育を受ける側にとって、有益な教育にするためには質の高い教員の確保が必要不可欠と言えます。教員研修などを強化し、知識や経験が豊富な先生を増やすことが重要です。
とくに、開発途上国は国際協力を活用しながら教員の質を高める必要があると考えられます。
3.安全な学校づくりの推進
子どもたちが安心して就学するためには、安全な学校であることが大切です。暴力がないこと、性別による差別がないこと、障害の有無による差別がないこと、などは安全な学校の条件といえます。
また、思わぬ事故につながらないよう、学校の施設や設備を新設・修理するなど、適宜必要な対応を進めていくことも必要です。
日本における取り組み事例

SDGsの目標4は、日本のさまざまな企業・自治体などが取り組んでいます。「教育」という難しいテーマではありますが、じつは意外にも自社でも実施できそうな取り組みは多いです。
実際に、日本ではどのような取り組みが取り入れられているのが、以下からご覧ください。
1.【企業】朝日新聞社
朝日新聞社では、SDGs目標4の取り組みとして、認知症を正しく理解するための出張講座や、中高生を対象としたSDGsの出張勉強会など、さまざまな形・テーマの教育機会を提供しています。
今できることや、今必要なことに目を向けているのが特徴、時代や需要にマッチした教育を提供している点が特徴です。
2.【自治体】山口県宇部市
山口県宇部市では、子どもの未来が輝くまちづくりとして、生きる力を育むことを目指しています。持続可能な開発を学ぶために必要な教育や、学習機会を推進し、「主体的に行動できる人を育てること」を重視。
単に知識を取り入れるだけではなく、体験や体感も視野に入れた学習機会を積極的に取り入れるようにしています。
出典:宇部市SDGs 「持続可能なまちづくりに向けて」|宇部市公式ウェブサイト
3.【企業】Kaien
Kaienが実施しているSDGs目標4の取り組みは、発達障害のある子どもたちにフォーカスした内容です。発達障害の子どもに特化したデイケアサービスを展開したり、発達面で不安を抱える大学生・専門学生のために就活サークル事業を行ったりするなど、子どもや若者が安心して教育を受けられるように活動しています。
また、すべての人が能力・資質にふさわしい教育を受けられるよう、個性を伸ばすこと及び社会に貢献できる大人になることを目指しています。
出典:KaienはSDGs達成に参画しています。コーポレートサイト : 株式会社Kaien
4.【学校】金沢工業大学
多くの学生に教育を行ってきた金沢工業大学では、「誰一人取り残さない」をモットーとした教育実現を目指しています。
まず、学生が教職員に相談しやすい環境を整えたり、専門のアドバイザーが就学状況を把握したりするなど、積極的なコミュニケーションに基づいて教育環境を提供しています。
また、先端技術のAIを活用するなど、学生の可能性を引き出すためにあらゆる方法を駆使し、必要に応じて導入しています。
世界における取り組み事例

世界では、SDGs4の目標における、さまざまな取り組みが実施されています。具体的にどのような取り組みが行われているのか、以下から見ていきましょう。
出典:SDG Industry Matrix日本語版 −食品・飲料・消費財| グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
1.レゴ
デンマークのおもちゃ会社として知られている「レゴ」。子どもに愛されるレゴブロックを生んだ会社です。
レゴでは、学習にフォーカスを当てた商品や、独自の教育プログラムを開発するなど、「学習支援」に重きを置いた取り組みを行っています。主に、子どもの才能を伸ばしたり、獲得した知識をしっかりと身につけたりすることができるよう、あらゆる方向から支援しているのが特徴です。
2.ウォルマート
アメリカに本部を置く「ウォルマート」は、世界最大規模でスーパーマーケットを展開している会社です。
同社が導入している取り組みは、大学生を対象に、工学に関する技術に触れる機会を設けたり、「見る・触れる・聞く・体験する」といった点を重視したイノベーションロードショーを実施したりしています。
また、STEM教育(科学・技術・工学・数学分野の教育)連合などへ支援を行っています。
3.Arcorグループ
「Arcorグループ」は、アルゼンチンで誕生した食品会社であり、主に製菓を専門としています。
同社が行うSDGsの取り組みは、従業員の教育の推進です。同社では、5万7,000時間にも及ぶトレーニングを提供。さらに、拠点の周辺の学校などへ質の高い教育及びトレーニングをサポートしています。
また、社外に対しては、会社が一丸となって多様性や生産性における意識向上のために、4万時間を超える持続可能性に関するトレーニングを提供しています。
4.ファッツェル・グループ
「ファッツェル・グループ」は、フィンランドの大手企業です。食品業界のなかでも規模の大きい企業であり、現在では、日本やロシア、スウェーデンなどにも拠点を置いています。
そんな同社のSDGs目標4の取り組み内容は、小規模カカオ生産農村の支援です。学校教育と連動しながら、カカオ農村で働く人(主に若者)に栽培に関するトレーニングを提供しています。
SDGs研修・体験型SDGsイベント
【SDGs研修】ワールドリーダーズ(企業・労働組合向け)

概要
- SDGs社会に合わせた企業経営の疑似体験ができるSDGsビジネスゲーム
- 各チームが1つの企業として戦略を立てて交渉し、労働力や資金を使って利益最大化を目指す
- オプションとして「SDGsマッピング」を行うことで学びの定着・自分ごと化
特徴
- 自分達の利益を追求しつつも、世界の環境・社会・経済も気にしなければならず、ビジネス視点からSDGsを感じ、考えることができる
- チームで戦略を練り様々な可能性を話し合う必要があるため、深いチームビルディングに繋がる
- 様々な選択肢の中から取捨選択して最適解を導く考え方を身につけることができる
【親子参加型職業体験イベント】キッズタウンビルダーズ(商業施設・企業・労働組合向け)

概要
- 体験を通じてSDGs目標の「質の高い教育」を学べる親子参加型ワークショップ
- 子どもが楽しみながらも本気で学べる、複数の職業体験を実施
- 会議室やホールなど企業様のイベントとしても開催可能
特徴
- あえて「映える」職業ではなくありふれた職業を選定している
- 合計で就業人口の7割を占める上位5つの職業をピックアップし、本質的な学びが得られる職業体験
- ファミリーが高い関心を持つテーマ性のあるイベントで集客・施設周遊を促進
【親子・子ども向け地域イベント】SDGsアドベンチャー(商業施設・自治体向け)

概要
- 体験を通じてSDGsを学べる親子・子ども向けワークショップ
- 子どもが本気で楽しめる複数の体験型アクティビティを実施
- すべてクリアした方にSDGs缶バッチをプレゼント
特徴
- ハッピーワールドの世界観を演出することで参加者が没入感をもって取り組める
- 海の環境やゴミの分別・再利用など、参加者は身近なことからSDGsを学べる
- ファミリーが高い関心を持つテーマ性のあるイベントで集客・施設周遊を促進
まとめ

今回解説した通り、まだまだ世界の教育現場における課題・問題は非常に多いのが現状です。ですが、意外にも私たちができる支援もたくさんあります。
日本は高い水準で小学校や中学校の卒業割合を維持できていますが、世界に目を向けてみると日本のように教育システムが整っていない国もあります。
まずは、世界の教育現場の現状について理解を深めることが、SDGsの目標4に寄り添うことになります。自社としては、オンライン研修を取り入れたり、従業員の資格取得を支援したりするなど、できることから初めてみてください。
SDGsのはじめの一歩を支援するSDGsイベント・研修とは?
SDGsのはじめの一歩を実現する「SDGsの社内浸透方法」とは?
進めるための具体的なステップを紹介!

自分ゴト化を促進!3分で分かるSDGs研修・イベントサービスの詳細動画
\SDGsイベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
SDGsとは
「SDGsについて学びたいけれど、何からはじめればいいのかわからない」
「世界中の人が質の高い教育を受けられるようになるために何かしたいけれど、どうしたらいいのかわからない」
そんなお悩みをお持ちの方におすすめなのが、「SDGsコンパス」です。
SDGsコンパスは企業、あるいは自治体の「SDGsへのはじめの一歩」を後押しするプロジェクトです。
年間で1000件ものイベントを行なっているIKUSAが、ワークショップや謎解きを通じて、SDGsについての知識を得るきっかけを作ります。
「イベントを楽しみながら、SDGsについての知識を得たい」
「SDGsの取り組みを会社や自治体で行いたいけれど、方法がわからない」
そう思っている方は、ぜひ資料をご覧ください。
SDGsコンパスの資料をダウンロードするこの記事を書いた人
SDGsコンパス編集部
SDGsコンパスは、SDGsに踏み出したい企業や自治体様の「はじめの一歩」を後押しするメディアです。SDGsの目標やSDGsの導入方法などのお役立ち情報を発信していきます。
関連記事