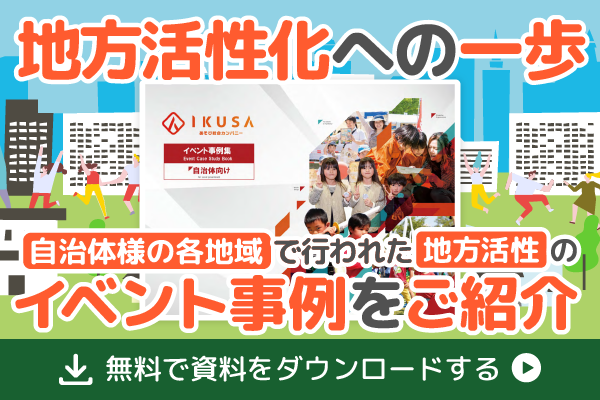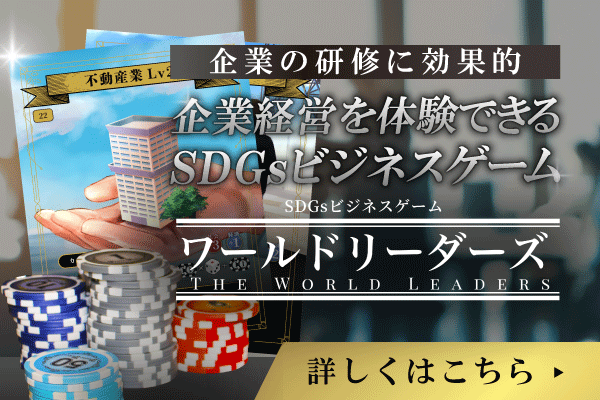フェアトレードに向けてできることは? 個人や企業での取り組みについて解説

いま、世界で「持続可能(サステナブル)な社会の実現」というキーワードが注目を浴びており、サステナブル持続可能性に関連した「フェアトレード」にも大きな関心が寄せられています。
フェアトレードは、労働環境の整備も含めて生産者の生活を向上させ、安定した生活環境を構築することを目的としています。そのため、途上国における「不当な労働条件」「違法な児童労働」「環境問題」など社会課題の解決に繋がる貿易の仕組みといえます。
そこで本記事では、フェアトレードに関する個人でできる取り組みや、企業ができる取り組み内容事例について解説します。
SDGsのはじめの一歩を実現する「SDGsの社内浸透方法」とは?
\SDGsイベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
フェアトレードとは?
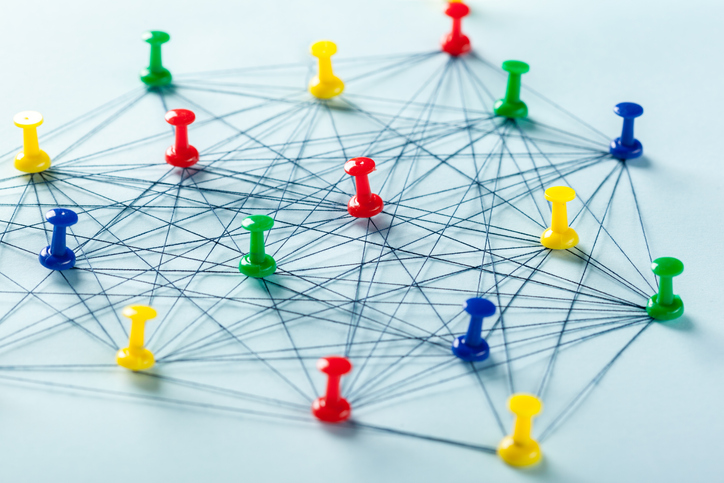
普段、私たちが使用している便利で安価な日常生活品には、途上国で生産されたものが数多く存在しています。しかし、安い価格で販売されている商品のなかには、途上国の生産者や労働者に大きな負担をかけ、さまざまな社会的問題を生み出しているものがあります。そのような社会的問題を解決するための取り組みが、「フェアトレード(公平・公正な貿易)」です。
フェアトレードとは、途上国で生産された原材料や商品を、適切な価格で継続して購入することで、途上国の発展や、生産者・労働者の自立を目的とした仕組みです。日本においては、まだまだ「フェアトレード」の認知度は低いですが、さまざまな企業が「途上国の発展」や「正しいと思う消費」に繋がるフェアトレード商品・サービスの提供や取り組みを実施しています。
出典: フェアトレードミニ講座|フェアトレードとは?|fairtrade japan|公式サイト (fairtrade-jp.org)
フェアではない貿易とは?
本来、取引とは双方にメリットがあるものですが、先進国と途上国の貿易には、豊かな国が貧しい国に対して、一方的に有利な(アンフェアな)条件で取引を行っている場合があります。アンフェアな貿易は、価格決定権が生産側にないため、生産国の利益が極端に少なくなります。
このような一方にのみ負担を強いる取引が「不当な賃金による労働」「貧困による児童労働」「大量の農薬使用による環境への負荷」など、途上国におけるさまざまな社会的問題を生み出している一因です。このフェアではない貿易が続いていることで平等な社会がの実現を妨げ、先進国と途上国における格差拡大に繋がっています。
フェアトレードの目的
フェアトレードとは、途上国で生産されたものを適切な価格で買い取ることで、途上国と先進国で広がり続ける格差を無くし、現地の地域社会や人がより豊かになることを目的としています。しかし、「フェアトレードは、単なる慈善活動だ」、「品質の低いものを高価格で購入する取り組みだ」と誤解され、その本質や目的が理解されていないケースも少なくありません。
フェアトレードは、どちらか片方が得をする仕組みではなく、買い手にもしっかりとしたメリットがあるうえで、下記のような途上国の発展や自立に貢献でき、アンフェアな貿易によって発生した社会的問題を解決するビジネスモデルです。
フェアトレードによる途上国のメリット
- 労働環境の改善
- 生産者の収入安定
- 自然環境の保護
- 伝統的な技術・文化の保護
- 学校や病院などインフラの整備
- 技術力の向上
出典:消費者も知っておきたい、フェアトレードのメリットとデメリット! 現状と問題点は? | MIRAI Times|SDGsを伝える記事が満載|千葉商科大学 (cuc.ac.jp)
SDGsの社内浸透にお困りですか? SDGsコンパスなら体験を通してSDGsを楽しく学べます!
個人でできるフェアトレードへの取り組み

フェアトレードへの取り組みは、生産者側のみにメリットがあるものではなく、消費者側にも「安全な環境で作られた、高品質な商品を継続的に購入できる」といったメリットが存在します。フェアトレードと認められている商品は、労働環境が整い、環境に悪影響を及ぼさない持続可能な生産システムによって作られているものです。そのような商品が市場に多く流通することで、消費者側は安心で安全な商品を長く使い続けることができます。
このように消費者側にもメリットがあるフェアトレードへの取り組みは、個人でも簡単に始めることができます。まず第一歩として、フェアトレードの目的や仕組みについてしっかりと理解しましょう。そして、買い物の際には、フェアトレードの対象となっている生産物、特に「認証ラベル」が付いた商品を積極的に購入することで、途上国の生産者や労働者の支援へと繋がります。ここでは、購入の際に対象となる商品と、代表的な認証ラベルについて解説します。
フェアトレード商品の代表例
フェアトレード商品の多くは、下記のような日常生活で使用している身近なものであり、いま使っているものから切り替えるだけで簡単に取り組みを始められます。また、近頃はカフェなどの飲食店で、フェアトレード商品を提供している店舗も多くあるため、外食の際にそのようなお店を積極的に利用することも、個人でできるフェアトレード活動のひとつです。
- コーヒー
- 紅茶
- カカオ
- スパイス・ハーブ
- 果物
- 加工果物
- ワイン
- オイルシード・油脂果物
- 切花
- コットン製品
フェアトレードの「認証ラベル」を目印にしてみよう
フェアトレード商品は市場に数多く流通していますが、独自の基準でフェアトレードと記載している商品も数多く存在しており、一般消費者にはどの商品を購入すれば途上国への支援になるか判別しづらいといったケースも少なくありません。
下記の2種類の認証ラベルは、世界的にも広く認知されている、代表的なフェアトレードを示すラベルです。厳しい基準をクリアした国際的なものですので、安心して購入できます。
FI フェアトレード認証ラベル(国際フェアトレードラベル機構)
国際フェアトレードラベル機構が定めた「経済的基準」「社会的基準」「環境的基準」をクリアした商品に付けることができる、認証ラベル。
WFTO フェアトレード保証ラベル(世界フェアトレード機関)
世界フェアトレード機関(WFTO)が定める10原則を順守した、加盟団体や組織が商品に付けることを許される認証ラベル。
出典:認証ラベルについて|フェアトレードとは?|fairtrade japan|公式サイト (fairtrade-jp.org)
出典:世界フェアトレード機構「フェアトレードにおける10原則」(PDF)
企業ができるフェアトレードへの取り組み

企業においても、フェアトレードへの取り組みを行うことは、企業のイメージアップや資金調達に繋がる、環境や社会に配慮した企業に対して投資を行う「ESG投資」の対象となるなどのメリットを得られるでしょう。
企業ができるフェアトレードへの取り組みの一例をご紹介します。
出典:消費者も知っておきたい、フェアトレードのメリットとデメリット! 現状と問題点は? | MIRAI Times|SDGsを伝える記事が満載|千葉商科大学 (cuc.ac.jp)
社内消費にフェアトレード商品を使用する
現在、企業が行っている事業にフェアトレード商品との関わりがない場合、フェアトレードに関する新規事業を手掛けるには多くの時間とコストがかかり、難しいのが現実です。まずは社内で日常的に使用するものをフェアトレード商品に変えるなど、下記のような簡単な取り組みから始めることで、今後の事業展開へのきっけとなるでしょう。
- 社員や接客に提供する飲み物(コーヒーや紅茶など)をフェアトレード商品に切り替える
- 社員食堂で提供しているメニューに、フェアトレード商品を取り入れる
- フェアトレードによって生産された衣類や工芸品を販売する社内イベントなどを行う
フェアトレード商品の販売
商品の製造・販売に関わる事業を展開している企業は、下記のような「原材料の見直し」や「仕入れ先の変更」など、直接的にフェアトレード商品に関連した取り組みを実施することが可能です。
- 自社で製造している商品の原材料を、フェアトレード認証を受けているものに変更する
- 自社でフェアトレードの明確な基準を定め、現地の生産者から直接買い付けを行う
企業や団体におけるフェアトレードへの取り組み事例5選

世界的にフェアトレード商品への注目が集まるなかで、日本でも多くの企業や団体がフェアトレードに着目しており、途上国の発展や自立へと繋がる、さまざまな取り組みを実施しています。ここでは、企業や団体が行っているフェアトレードに関する取り組み事例を5つ紹介します。
イオン株式会社「持続可能なカカオの調達に向けた取り組み」
イオン株式会社では、持続可能な自然資源の活用と事業活動の継続的な成長の両立を目指しており、自社の基準である「イオン 持続可能な調達原則」に基づいた調達先を選定しています。イオンプライベートブランドで使用するカカオは、下記のような持続可能性の裏付けがとれたものへ切り替えています。
- イオンが認定する第三者認証を取得した原料を使用していること(国際フェアトレード認証など)
- 生産者や労働者の方々が抱える社会課題の解決に向けたプロジェクトを、イオンが直接、支援し生産地の持続的な発展に寄与していること
また、イオンでは原材料の調達基準の設定以外にも、フェアトレードへの取り組みとして「国際フェアトレード原料調達ラベル(FSIラベル)」の認証を取得したチョコレートやジャムなどの生産・販売を行っています。
出典:フェアトレード | 社会の取り組み | イオンのサステナビリティ | イオン株式会社 (aeon.info)
株式会社キャメル珈琲「一杯のコーヒーに込めた地球への思い。カルディコーヒーファームの取り組み」
カルディコーヒーファームを運営している株式会社キャメル珈琲では、フェアトレードなど社会に貢献できる活動を知るきっかけとして「地球にいいことしてる?」をスローガンに、従業員一人ひとりが自分にできることを考えられる環境作りに取り組んでいます。
また、フェアトレード商品の販売に繋がる取り組みとしては、フェアトレード認証の「ウーマンズハンドコーヒー」(※)を商品化。一般消費者にフェアトレードを知ってもらうきっかけとして、2012年10月3日〜10月31日までに「ウーマンズハンド・フェアトレードブレンド」を10%OFFで販売する「フェアトレードコーヒーキャンペーン」を実施しました。
商品を購入した顧客からは、美味しいとの反応が多く、多くのリピーターの獲得に繋がっています。消費者に商品の良さや美味しさから興味を持ってもらうことで、生産者の思いや現状に関心を抱くきっかけ作りを続けています。
出典:インタビュー|fairtrade japan|公式サイト (fairtrade-jp.org)
千葉商科大学『地域や企業を変えていこう!学生カフェから発信するフェアトレードとは?』
千葉商科大学のサービス創造学部では、2020年にフェアトレードをテーマにしたコミュニティカフェを開催。参加した学生は、食材の調達から販売まですべての運営を任され、フェアトレードの現状や原価の高いフェアトレード商品を扱うことの難しさを体感したうえで、なぜフェアトレードに取り組まなければならないのか、その重要性を学びました。
プロジェクトに携わった学生からは、「周りの人にも広めたい」「毎朝フェアトレードコーヒーを家族と飲むようになった」などの意見があり、参加した学生自身のフェアトレード意識の高まりだけでなく、その周辺にまでフェアトレードに関わる取り組みが広がると期待されています。
出典:インタビュー|fairtrade japan|公式サイト (fairtrade-jp.org)
株式会社NTTデータ「できることからやってみよう!」が始まり。 日常の社内消費にフェアトレード製品を取り入れることの意義
株式会社NTTデータでは、海外の企業が社内カフェなどでフェアトレード製品を使用しているとの事例を知り、自社でも「できることからやってみよう!」をテーマに、下記のような取り組みを実施しています。
- 来客用コーヒーや社内スペースでフェアトレードコーヒーを採用
- フェアトレード月間を定め、フェアトレード認証品を使用したワークショップを開催
- 株主総会のお土産にフェアトレード認証製品のケーキを採用
まずは、会社が率先してフェアトレード製品を使用することで、社員に「いつも買っているものをフェアトレード製品へ替えればよい」 という意識が浸透する環境作りを行っています。
出典:インタビュー|fairtrade japan|公式サイト (fairtrade-jp.org)
ホットマン株式会社「老舗タオルメーカー、フェアトレード製品へのチャレンジ」
ホットマン株式会社は、2013年には国際フェアトレード認証を取得しており、日本で初めてフェアトレードコットンタオルの生産・販売を手掛けたタオル専門メーカーです。全国の直営店を通して、フェアトレードの認知度向上に努めており、さまざまな世代の消費者や企業、市役所などの公的機関からフェアトレードに関連した問い合わせが増加するなど、タオルを通じて幅広い層のフェアトレードへの関心を高めています。
また、2014年には、第一紡績が主催している「セネガル産フェアトレード認証コットンセミナー」に出席。ジェトロやフェアトレード・ラベル・ジャパン、イオントップバリューと並び、フェアトレードの取り組みについて紹介されるなど、注目を浴びています。
出典:インタビュー|fairtrade japan|公式サイト (fairtrade-jp.org)
SDGs研修・体験型SDGsイベント
【SDGs研修】ワールドリーダーズ(企業・労働組合向け)

概要
- SDGs社会に合わせた企業経営の疑似体験ができるSDGsビジネスゲーム
- 各チームが1つの企業として戦略を立てて交渉し、労働力や資金を使って利益最大化を目指す
- オプションとして「SDGsマッピング」を行うことで学びの定着・自分ごと化
特徴
- 自分達の利益を追求しつつも、世界の環境・社会・経済も気にしなければならず、ビジネス視点からSDGsを感じ、考えることができる
- チームで戦略を練り様々な可能性を話し合う必要があるため、深いチームビルディングに繋がる
- 様々な選択肢の中から取捨選択して最適解を導く考え方を身につけることができる
【親子参加型職業体験イベント】キッズタウンビルダーズ(商業施設・企業・労働組合向け)

概要
- 体験を通じてSDGs目標の「質の高い教育」を学べる親子参加型ワークショップ
- 子どもが楽しみながらも本気で学べる、複数の職業体験を実施
- 会議室やホールなど企業様のイベントとしても開催可能
特徴
- あえて「映える」職業ではなくありふれた職業を選定している
- 合計で就業人口の7割を占める上位5つの職業をピックアップし、本質的な学びが得られる職業体験
- ファミリーが高い関心を持つテーマ性のあるイベントで集客・施設周遊を促進
【親子・子ども向け地域イベント】SDGsアドベンチャー(商業施設・自治体向け)

概要
- 体験を通じてSDGsを学べる親子・子ども向けワークショップ
- 子どもが本気で楽しめる複数の体験型アクティビティを実施
- すべてクリアした方にSDGs缶バッチをプレゼント
特徴
- ハッピーワールドの世界観を演出することで参加者が没入感をもって取り組める
- 海の環境やゴミの分別・再利用など、参加者は身近なことからSDGsを学べる
- ファミリーが高い関心を持つテーマ性のあるイベントで集客・施設周遊を促進
まとめ

近頃、よく見聞きする「フェアトレード」という言葉ですが、正しい内容や目的はあまり理解されておらず、まだまだフェアトレードへの取り組みが十分に行われているとはいえません。
まずは、消費者や企業が、原材料・製品が作られている背景の理解や価格に対する認識を改めること。そして、社会全体が平等になるような生産・消費行動を心がけることがフェアトレードへの取り組みを始める第一歩となるでしょう。
いくつかの企業は、フェアトレード関する取り組みをすでに始めており、フェアトレード商品の販売やイベントなども徐々に増えてきています。個人・企業に関わらず、いつも使っているものをフェアトレード商品に切り替えることや、イベントへの参加など、できることから始めてみてはいかがでしょうか。
SDGsのはじめの一歩を支援するSDGsイベント・研修とは?
SDGsのはじめの一歩を実現する「SDGsの社内浸透方法」とは?
進めるための具体的なステップを紹介!

自分ゴト化を促進!3分で分かるSDGs研修・イベントサービスの詳細動画
\SDGsイベント・研修向け体験型アクティビティの資料はこちら/
【関連記事】
SDGsとは
フェアトレードとは? 身近な商品や認証ラベルを紹介!
「SDGsは道しるべ」ホットマン株式会社代表取締役社長・坂本将之
ESG投資とは?SDGsとの違いやメリットをわかりやすく解説
フェアトレードの5つの問題点とは? 解消するための7つの方法
この記事を書いた人
SDGsコンパス編集部
SDGsコンパスは、SDGsに踏み出したい企業や自治体様の「はじめの一歩」を後押しするメディアです。SDGsの目標やSDGsの導入方法などのお役立ち情報を発信していきます。
関連記事